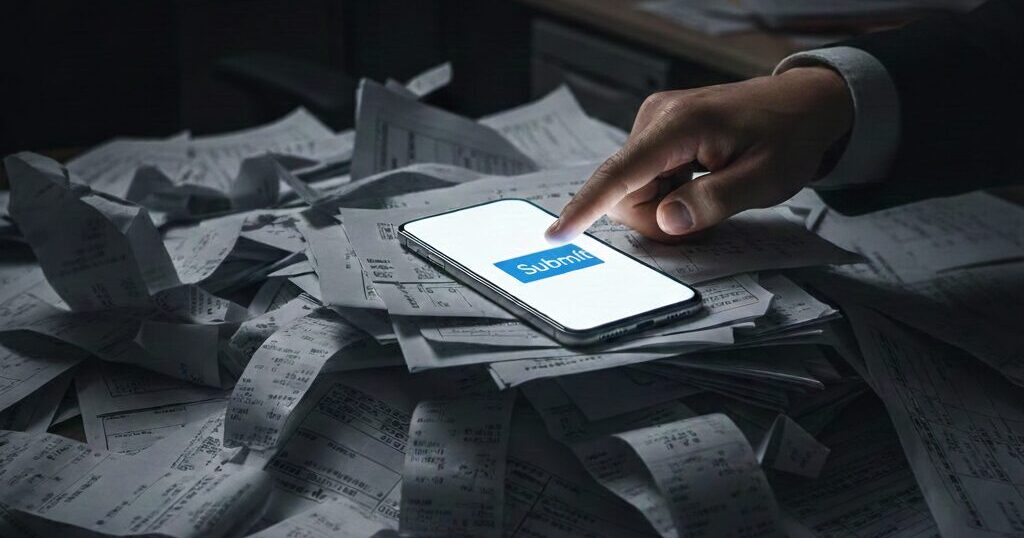年末調整についてはデジタル化するためのサービスも登場していますが、まだまだ「紙」から脱しきれていないところが少なくないのが実情です。今回は、その理由について、現場で感じている要因をまとめておきたいと思います。
目次
年末調整、紙の申告書が約4割
みなさん、こんにちは。京都の税理士、加藤博己です。
先日、会計ソフトベンダーの弥生さんから、年末調整に関する興味深い調査結果が公表されていました。
弥生、年末調整・法改正への対応状況を調査(出典:「令和7年度 年末調整に関する意識調査」弥生調べ)
この調査結果によると、年末調整の申告書の配付・回収方法として「紙での提出」が全体の約4割を占めている、とのこと。
驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、私は「やっぱりそうか」という感覚の方が大きいです。
特に中小企業となると、この「紙」の割合はもっと高くなるのではないでしょうか。
デジタル化の流れは間違いなく来ています。
国税庁も「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」なるものを無償提供していますが、残念ながら、これはごく一部しか対応できませんので、実務で使うには不十分です。
そのため、多くの民間ソフトベンダーさんが、デジタルツールを開発・提供してくれています。
しかし、良いツールがあっても、実際に現場で使いこなせない、あるいは導入を躊躇してしまう壁が存在します。
ツールがあってもデジタル化できない理由
では、なぜデジタル化の波に乗れない企業がこんなに多いのでしょうか?私なりに見てきた要因としては次のようなものが挙げられます。
1. 世代の壁とITリテラシーの問題
これが、一番大きな問題かもしれません。
デジタル化する場合、従業員一人ひとりが、自分のスマホやパソコンから情報を入力して申告書を作成することを前提にしています。
ところが、特に中小企業では、様々な年齢層の方が一緒に働いています。
従業員の中に、年配の方が混じっている場合、
「あの人はパソコンもスマホも苦手だし、デジタル申告だと対応できない」
と、導入する側が二の足を踏んでしまうケースがあります。
小さな中小企業だと、ビジネス用のメールですら一般的でないという職場もまだあります。特に現場作業に携わる従業員が多い事業の場合は特にです。
そうしたデジタル環境に慣れていない方がいると「紙の方が結局、全員対応できるから楽」という判断になってしまいがちです。
こうした状況を考慮して、freeeは「LINEで簡単に申告できますよ」といった案内もしていますが、それでも「慣れない作業への抵抗感」はなかなか手ごわい壁です。
2. コスト負担とメリットの比較
新しいソフトやサービスを導入するには、当然ながら費用がかかります。
「コストをかけてデジタル化するメリットが、どれだけあるのか?」という点について、経営者や経理担当者に十分伝わっていないのも、デジタル化が進まない大きな理由の一つでしょう。
-
デジタル化で経理担当者の負担が減る
-
書類の不備が減り、税理士とのやり取りがスムーズになる
-
将来的な法改正にも対応しやすい
こうしたメリットが、導入コストや従業員の教育コストを上回ると腹落ちしなければ、「慣れた紙のままでいいや」となってしまうのは当然です。
また「税理士に紙の書類を提出さえすれば、あとはなんとかしてくれる」という意識が残っている企業もあります。
企業の担当者側が「年末調整は税理士任せ」と割り切ってしまっていると、デジタル化による社内工数の削減というメリットを感じにくくなります。
我々税理士側からすれば、紙のままだと回収やチェックなどの作業に膨大な時間と手間がかかっています。
この税理士側の負担が大きくなれば、いずれは値上げという形で、その分のコストを企業にも負担していただくことになるでしょう。
デジタル化は、企業と税理士、双方の負担を減らすための投資だと捉えていただくべきかと思います。
避けて通れないデジタル化の未来
今のところ、私の周りで言えば、この「世代の壁」と「コスト負担(とメリットの比較)」が、年末調整のデジタル化を阻む主な理由となっています。
しかし、このまま「紙」にこだわり続けるわけにはいかないのが現状です。
年々複雑化する年末調整
年末調整の仕組みは、控除の種類の増加や税制改正によって年々複雑化しています。
書類の紙を渡されても、その申告書に書かれている「意味」を理解して記入できている人は、ほとんどいません。
多くの人は、昨年の書類を見ながら、あるいは経理担当者に聞きながら、とりあえず空欄を埋めているのが実情でしょう。
デジタルの方がミスが減る
そうであれば、書類を渡して記入させるよりも、
「あなたは扶養している人はいますか?」
「生命保険料を支払っていますか?」
といった、誰にでもわかる「質問形式」で情報を入力・提出できるように変えていく方が、紙の申告書に記入するよりも正確性は向上するでしょう。
一度、質問形式のデジタル申告に慣れてしまえば、もう昔の「紙」の申告書には戻りたくなくなるはずです。
経理担当者のチェック工数も劇的に減りますし、何より、書類の紛失や書き損じといった人によるミスが大幅に削減されます。
デジタル化の前に年末調整の「仕組み」を簡素化すべき
とはいえ、一番思うのは、そもそも年末調整の仕組み自体をもっと簡素化すべきではないかということです。
国が求める申告事項が多すぎるから、システムが複雑になる。
デジタル化はもちろん大事ですが、それに加えて、国民の大多数にとって不要な手続きは大胆に削減していく。
「国民全員が理解できて、誰もが簡単に申告できる」。
この大原則に立ち返って、税制そのものを見直せば、「年末調整のデジタル化」なんて、わざわざ検討する必要もなくなります。
一番の効率化は「不要な仕事をなくすこと」なんですけどね・・・。
投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長
-
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。
40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。
現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
最新の投稿
 確定申告2026年2月26日「確定申告って自分でできる?」に対する私なりの考え方
確定申告2026年2月26日「確定申告って自分でできる?」に対する私なりの考え方 経理2026年2月22日経理のルールは経理だけが知っていればいいわけではない、というお話
経理2026年2月22日経理のルールは経理だけが知っていればいいわけではない、というお話 経理2026年2月19日経理が苦手な人ほど「ルール」が必要。迷いをゼロにする3つのメリット
経理2026年2月19日経理が苦手な人ほど「ルール」が必要。迷いをゼロにする3つのメリット 税金2026年2月15日お金に「名前」をつけて管理する。納税のストレスを減らすためのシンプルな習慣
税金2026年2月15日お金に「名前」をつけて管理する。納税のストレスを減らすためのシンプルな習慣