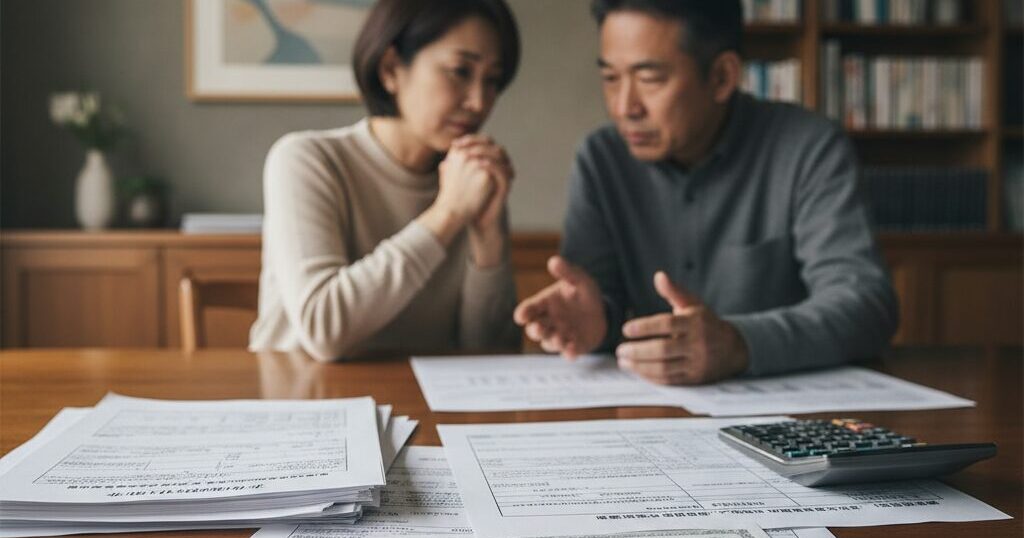年末調整の書類のひとつに「給与所得者の保険料控除申告書」があります。ほとんどの方は保険会社から受け取った証明書をみながら転記するだけかもしれませんが、一般の方があまり意識していない注意点がありますので、確認しておきましょう。
目次
保険料の控除を受けられるのは誰?
みなさん、こんにちは。京都の税理士、加藤博己です。
年末調整の時期になると、多くの書類を会社に提出しますが、従業員の方々にとっては、言われた通りに記入するだけ、というケースが多いのではないでしょうか。
そうした書類のひとつとして「給与所得者の保険料控除申告書」があります。
この書類、保険会社から届いたハガキを見ながら金額を転記するだけ、という方がほとんどだと思います。
しかしながら、「誰が」保険料の控除を受けられるか、きちんと意識している方はどれだけいるでしょうか?
例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。
-
生命保険の契約者: 妻
- 保険料の負担者: 夫
この場合、年末調整で生命保険料控除を受けられるのは、契約者ではなく、保険料を実際に負担している夫となります。
控除の要件
実際には、生命保険料控除を受けるには、保険料を負担している以外に
「保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするもの」
国税庁タックスアンサー No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等 より
という条件も必要ですが、通常は保険会社の方で生命保険料控除を受けられるような契約にしてくれているでしょうから、それほど心配する必要はありません。
そのため、「契約者」ではなく、「保険料を負担した人」がその保険料について生命保険料控除を受けることができる、という点がポイントとなります。
なお、個人年金保険について控除を受けるには受取人に制限があり
「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること。」
が必要です。生命保険料控除に比べると受取人の範囲が少し狭まっている点にご注意ください。
その保険、受取人は誰ですか?
将来、保険金を受け取るケース
今、年末調整で控除を受けている生命保険などについては、いつか満期を迎えたり、被保険者の方が亡くなられて保険金が支払われたりする日が来ます。
このとき、受け取った保険金には、所得税、贈与税、あるいは相続税のいずれかが課税されます。
ここでは、「保険料負担者」と「受取人」の関係性が重要になってきます。
満期保険金を例に、どの税金がかかるかは次のようになります。
| 保険料負担者 | 受取人 | 課税される税金 |
| 夫 | 夫 | 所得税 |
| 夫 | 妻 | 贈与税 |
夫婦間の契約と贈与税の落とし穴
先ほどの例をもう少し詳しく確認しておきましょう。
契約者:妻、保険料負担者:夫 とします。
-
受取人:夫の場合
-
税金:所得税
-
夫が自分で積み立てた保険金を自分で受け取る形なので、増えた部分が一時所得として所得税の対象になります。
-
一時所得は、ザックリ言えば、受け取った保険料から支払った保険料を差し引いて、さらに「特別控除額(最高50万円)」を差し引いた金額の2分の1に税率をかけて計算します。
-
-
受取人:妻の場合
-
税金:贈与税
-
夫が保険料を払って積み立てた財産を、満期時に妻が受け取る、つまり夫から妻へ財産が贈与されたとみなされます。
-
贈与税は、年間110万円の基礎控除を引いた後の金額に税金がかかります。
-
一般的には、一時所得として2分の1課税となる所得税の方が、税金が少なくなることが多いでしょう。
過去の年末調整との整合性
ここで問題になるのが、「実際に誰が保険料を負担したか」という点です。
例えば、「契約者:妻、保険料負担者:夫、受取人:妻」という契約で、いざ満期が来て多額の贈与税がかかると知ったとき
「いや、実際には妻が自分のお金で保険料を払っていたんだ!」
と主張したとしても、その主張がどこまで通るでしょうか。
もし本当に妻が自分の口座から保険料を払っていたのであれば、そもそも過去の年末調整で夫が生命保険料控除を受けていたことは誤り、ということになります。
なぜなら、控除を受けられるのは「保険料を負担した人」だからです。
保険を契約する際に、「誰が払うのか」「誰が受け取るのか」を明確にし、その通りに年末調整の書類も記入することが、将来の税金トラブルを防ぐうえで非常に重要なのです。
国税庁の年末調整のQ&Aでも、わざわざ以下のような注意書きを設けています。
問8注書き
保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、その生命保険金を受け取った場合、贈与税や相続税の対象となります。
わざわざ記載しているということは、それだけ「注意してね」という意味が込められていると考えるべきでしょう。
「たかが書類」でもあとで影響が出ることもある
年末調整ではスルーされるが・・・
今回のケースで厄介なのは、年末調整の時点で、税務署が保険料控除申告書に記載された契約者や受取人の欄について細かくチェックすることは、まずないという点です。
会社の経理担当者にしても、大量の書類を処理する中で、そこまで細かくチェックすることはできないでしょう。
控除証明書に書かれた内容を基に、税金を計算するだけです。
問題が表面化するのは、将来、満期保険金などのまとまった金額を受け取って、所得税または贈与税、もしくは相続税の申告が必要になった際です。
年末調整の資料が判断材料に
もし、夫と妻のどちらのお金から保険料が支払われていたのかが明確でない場合、過去に提出された年末調整の申告書が、「保険料負担者は誰であったか」という判断の材料の一つになる可能性もあります。
毎年、「保険料の証明書を見ながら金額を転記するだけ」と考えている年末調整の書類ですが、実はその一つ一つが、将来の保険金にかかる税金に影響を与える内容を含んでいます。
生命保険を契約する際は、「現在の生命保険料控除」だけでなく、「将来の受取時の税金」まで視野に入れて、契約者、保険料負担者、受取人の関係を整理し、そして年末調整の書類も正確に記入するよう、ご注意ください。
税金は知っているか知らないかで大きく結果が変わることがあります。少しでも不安な点があれば、お近くの税理士に相談することをお勧めします。
投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長
-
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。
40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。
現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
最新の投稿
 仕事術・勉強法2026年1月18日その手順は何のため?実効性のある仕組みを作るための考え方
仕事術・勉強法2026年1月18日その手順は何のため?実効性のある仕組みを作るための考え方 経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事
経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事 仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない
仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない 仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか?
仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか?