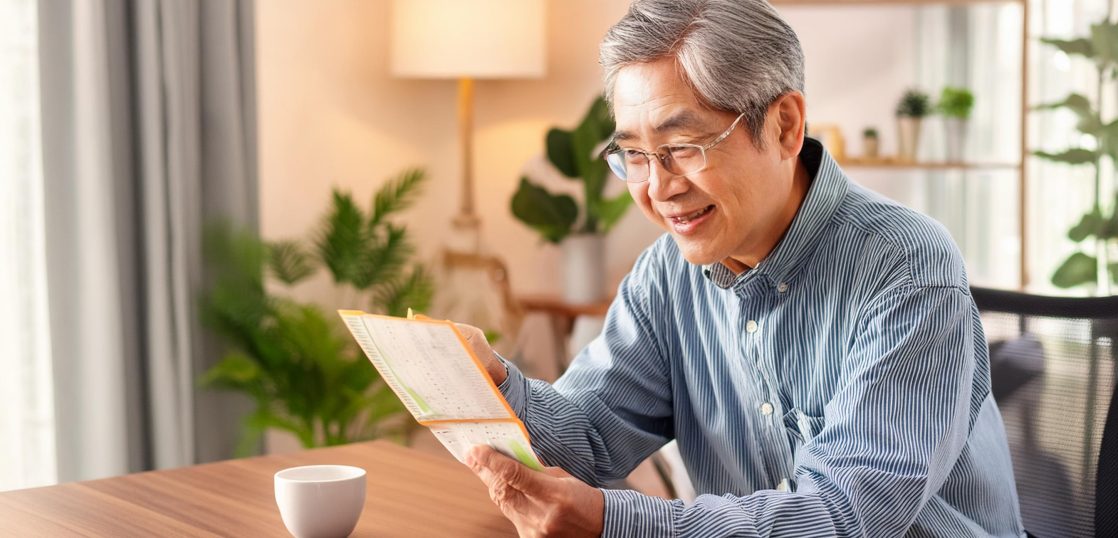贈与についてのご相談をいただくこともありますが、その際にお伝えしているのは最初に「いくら」と「いつまで」を決めましょうという点です。
目次
相続や贈与の仕事もやっています
相続や贈与については、普段このブログで取り上げることも少なく、ホームページのメニューでも大々的に打ち出していませんが、ご相談などを受けることは当然ありますし普通に対応しています。
「相続や贈与に強い!」とか「資産税専門!」といった税理士ではありませんが、いつそのようなご相談を受けるかわかりませんので、普段から情報収集や勉強は欠かしていません。
ご相談いただく内容としては、ご不幸があった場合の相続税の申告もありますが、普段はどちらかと言えば、お元気なうちに贈与を考えているけれどもどうしたらいいか、といったものの方が多いです。
今回は、こうした贈与に関するご相談を受けたときの、最初のポイントについてまとめておこうと思います。

最初の質問は「誰に」「いくらを」「いつまでに」
贈与を検討する際の最初の質問
ある程度年齢が進むと「終活」というほどのことではなくても、次の世代に財産を残してあげたいと考える方は増えてきます。
ただこうした方達から相談を受ける際に、最初にでてくる質問は
「どんな風に贈与したらいい?」
「どうしたら税金が少なくて済む?」
といったものが多いように感じます。
これだけでは、こちらとしては何も回答できませんので、最初に
「誰に贈与をしたいですか?」
「最終的に総額でどれだけ贈与したいですか?」
「その金額を何年間くらいかけて贈与したいですか?」
という3つの点を伺うことにしています。
こうした質問をすると「誰に」という点はある程度イメージをお持ちのことが多いですが、あとの2点については「わからない」「決めてない」という回答が返ってくることがほとんどです。
亡くなる時期がわからないから難しい
税金の観点から考えたとき贈与が難しいのは
「人はいつ亡くなるかわからない」
からです。
例えば、ご存じの方も多いかもしれませんが、相続人となる人などに暦年贈与という形で贈与した人が亡くなった場合、3年以内の贈与は相続税の計算に含めることになります。
※法律の改正があり、今年以降7年以内まで順次対象期間が拡大されます。
亡くなる時期がわかっていれば、贈与のタイミングや金額などをそこに合わせて検討するといったことも可能となりますが、そんなことは実際には不可能です。
では逆に「重い病気にかかって先が長くないので贈与したい」と相談を受ければなんとかなるかというと、先ほどのような制度もあり、その時点ではできることは限られています。
だからこそ、贈与については前提条件を置いた上で検討して、時間をかけて必要に応じて見直すことが大事です。
その前提条件を置くための質問が「誰に」「いくらを」「いつまでに」となるわけです。
全体像をイメージしてからやるべきことを検討する
贈与を検討する際には「いくら」と「いつまで」が最初のポイントとなると書きましたが、これってどちらかというと税金を試算するために前提を置くための作業です。
実際に贈与を考える上では、あとで相続人の中で争いが起きないよう配慮する、ご本人の生活資金が不足しないように配慮する、など単純に税金の多寡だけで決められない要素が多々あります。
とはいえ「税金がどれくらいかかるのか」というのは多くの方が持つ不安ですから、税額のイメージをまず持ってもらうことは悪いことではないでしょう。
贈与に限った話ではありませんが、何かを検討する際にはまず全体像をイメージすることが大事です。
今回のケースで言えば
- 誰に
- 総額でいくらの金額を
- いつまでに
という点が全体像をイメージする上で必要となる情報です。
そこから検討を加えていった結果として、当初の想定とはまったく異なる内容に落ち着くことも当然ありますが、ご本人が考えたいわゆる「たたき台」のようなものを準備した上で進めないと
「なんか思ってたのと違う・・・」
という内容になってしまう恐れがあります。
贈与を検討する際には、ここに書いたこと以外にも様々な要素を踏まえて行うことになりますが、最初におおまかなイメージを持っていると話が進みやすくなりますし、贈与するご本人も内容を理解しやすくなります。
これから贈与することを考えているという方については、「いくら」と「いつまで」をまずイメージしていただくことをお勧めします。
投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長
-
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。
40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。
現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
最新の投稿
 仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由
仕事術・勉強法2026年2月1日散歩中の音声インプットを再開した理由 ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット
ブログ・HP2026年1月29日自分の考えを文章にまとめることのメリット 仕事術・勉強法2026年1月25日常に「間」を意識して話を聴けていますか?
仕事術・勉強法2026年1月25日常に「間」を意識して話を聴けていますか? 仕事術・勉強法2026年1月22日動画は倍速で視聴しても、話し方は0.7倍速くらいを意識する
仕事術・勉強法2026年1月22日動画は倍速で視聴しても、話し方は0.7倍速くらいを意識する