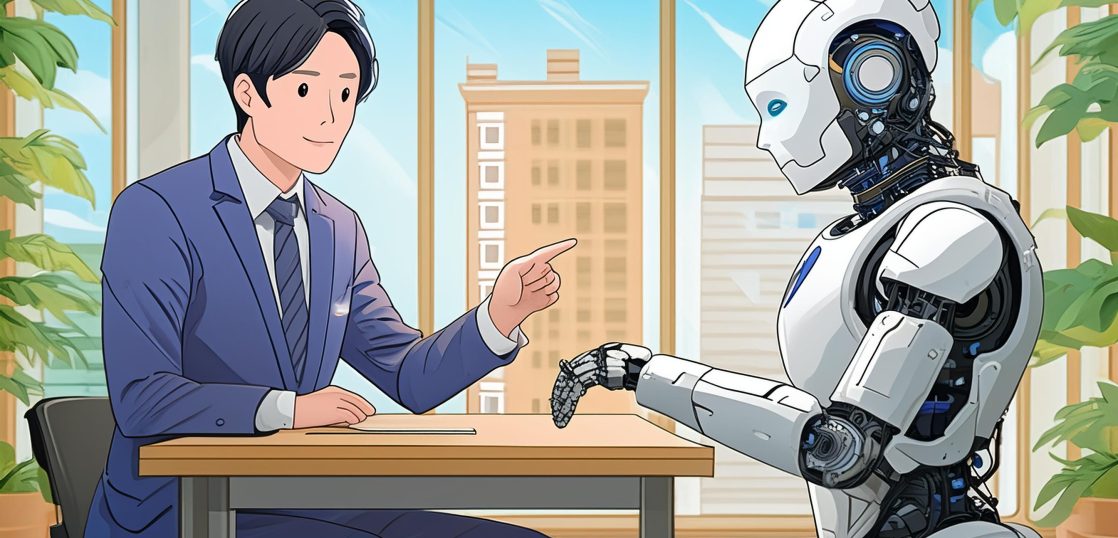組織で仕事をしていると「なぜ自分の意を汲んで行動してくれないんだろうか」と思うことはありませんでしょうか?今回はこうした状況についての私見をまとめてみます。
会社員時代、いつもイライラしてました
会社員として過ごした時代が約20年弱ありました。そうした期間のうち、部下を持っていた時期も当然あります。
今思い出しても、部下を持っていたときは常に「イライラ」していた気がします。
イライラの原因は
「なぜこちらの思った通りに仕事をしてくれないのか」
「なぜそんな判断をするのか」
「なぜ一から十まで説明しないと理解してくれないのか」
といったことだったと思います。
さらに、部下を持つようになった時期と海外で働いていた時期がかなり重なっていましたので、言葉の壁や文化の壁もありなおさらイライラ・・・。
そうした状況にいる間は中々気づけなかったのですが、会社を辞めてから冷静に考えてみると、あの頃の自分って
「自分の分身」
を求めていたんだなとあるとき気づきました。
気づいた後もしばらくは
「自分の分身がいたら仕事が楽だろうな」
と思っていた時期がありますが、今は
「他人に自分と同じように判断や行動をしてもらうのはムリ」
と考えるようになりました。
生まれも育ちも違う、要するにバックグラウンドが異なる人に対して自分と同じものを求めてもうまくいくわけないのは当然と言えば当然なんですが、こうした考え方が腹落ちするまで結構時間がかかってしまいました。

「自分の分身」を前提としない仕組みづくり
「自分の分身」を他人に求めるのが現実的でないとすれば、組織として仕事をする上でどうすべきか。
もし自分の判断基準に沿って仕事をして欲しいのであれば、その判断基準を「言語化」して伝えるしかありません。
基本的な作業の場合は、例えば「マニュアル」や「チェックリスト」が該当します。
「この手順で仕事を進めてほしい」「この点が間違っていないか作業後にチェックしてほしい」といった内容を「言語化」して相手に伝えるわけです。
こうすれば(マニュアル通りに仕事をしてくれるという前提は必要ですが)、自分の判断基準に沿って仕事をしてもらうことが可能となります。
その一方で「作業だけならそれでもいいけど、マネジャーとして活躍するレベルまで育ってほしい人もいる」というケースもあるでしょう。
こうしたケースも考え方は同じだと思っています。自分が考えていること・判断の基準としていることを「言語化」して伝えていくしかありません。
どのような形で言語化するかですが、例えば組織としての「方針」「行動指針」、古くさい言い方で言えば「社是」とか「社訓」、最近だとミッション、ビジョン、クレドとかこういった形になってくるでしょう。
全体としての方針を決めた上で、それとリンクした形で個人別の人事評価基準を明示して、その方向に沿って行動してもらった場合は昇級などといった形で応えるということが必要となります。
要するに自分が考えている方向と「だいたい」同じように進んでもらうためには「仕組化」が必要ですし、会社の方針や人事評価といったものはそのための「仕組み」だということです。
ということは、トップの人がその場の思いつきで判断するようなことをしている場合には、こうした「仕組み」は機能しません。
機能しないというか、そもそも「仕組み」に落とし込むことができません。
まずトップの方が
「自分はどのような方針で判断しているのか」
という点について、「感覚」ではなく「言葉」に落とし込む必要があります。
「言葉」に落とし込んだ後に、組織内に浸透させて行くことになりますが、その方法として昔であれば(今も??)朝礼で全員で声に出して読み上げるとか、カードに書いたものを全員に配布して定期的に確認するなどやり方はいろいろあるでしょう。
「自分の分身」の意見には必ず賛成する?
ちなみに余談ですが、今後AIが発達すれば例えば過去に自分で書いた文章などを読み込ませることで、自分と同じ考え方をしてくれる分身ができる可能性はあるでしょう。
このような状況になって、仮に「自分の分身」に仕事を依頼できるとして、その結果に100%満足・同意するのだろうかという疑問が実はあります。
「これでも悪くないんだけど、ちょっと違うんだよね」みたいな感じで反対意見を言うんじゃないかと。
意外と人はいい加減なものなので、自分の考えに沿ったアウトプットであっても、その内容を客観的に確認できると違う判断をするかもしれません。
こうした曖昧な部分って誰しも持っているものですから、自分の考えや判断基準を「言葉」に落とし込むのは、実際には簡単なことではありません。
ただそれでも一緒に働くひとに「だいたい同じ」方向を向いて仕事をしてもらいたいのであれば、判断してもらう際の拠り所となるものは提示する必要があります。
「自分のところの組織がうまく機能していない」と感じる場合は、自分の考えをきちんと形にして伝えられているか一度見直してみてはいかがでしょうか。
投稿者

- 加藤博己税理士事務所 所長
-
大学卒業後、大手上場企業に入社し約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。
31歳のとき英国子会社に出向。その後チェコ・日本国内での勤務を経て、38歳のときスロバキア子会社に取締役として出向。30代のうち7年間を欧州で勤務。
40歳のときに会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
中小企業の経営者と数多く接する中で、業務効率化の支援だけではなく、経営者を総合的にサポートするコンサルティング能力の必要性を痛感し、「コンサル型税理士」(経営支援責任者)のスキルを習得。
現在はこのスキルを活かして、売上アップ支援から個人的な悩みの相談まで、幅広く経営者のお困りごとの解決に尽力中。
さらに、商工会議所での講師やWeb媒体を中心とした執筆活動など、税理士業務以外でも幅広く活動を行っている。
最新の投稿
 経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事
経営管理2026年1月15日社長の頭の中の「モヤモヤ」をスッキリさせるお仕事 仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない
仕事術・勉強法2026年1月11日「手書き」も時と場合によっては悪くない 仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか?
仕事術・勉強法2026年1月8日その「掛け合わせ」、ダメって決めたのは誰ですか? 仕事術・勉強法2026年1月4日日々の小さな行動を始められない人への「習慣化」のススメ
仕事術・勉強法2026年1月4日日々の小さな行動を始められない人への「習慣化」のススメ